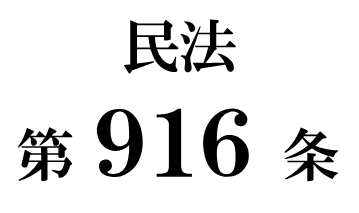民法第1012条 遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2項
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3項
第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
意訳
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現するために相続財産の管理のほか、実現に必要な一切の行為をする権利と義務をもつ。
2項
遺言執行者がいる場合には、遺言執行者のみが(遺言書にかかれた)遺贈を実行することができる。
3項
以下の条文の規定は遺言執行者に対して適用する。
・民法第644条「受任者の注意義務」
・民法第645条「受任者による報告」
・民法第646条「受任者による受取物の引渡し等」
・民法第647条「受任者の金銭の消費についての責任」
・民法第650条「受任者による費用等の償還請求等」
条文解説
本条は法改正により2019年に施行された条文です。
この改正で条文中に「遺言の内容を実現するため」という文言が追加されました。
具体的な権限の範囲は遺言書に書かれた内容によって異なりますが、ポイントは『遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務をもつ』ことであり、遺言の実現によって不利益を受ける人がいたとしても、それが遺言に書かれた内容であれば実行できるということです。
過去の裁判で、遺言書に書かれた内容と相続人の利害が対立する場合の遺言執行者の任務について争われたことがあり、その判決のなかで『遺言執行者の任務は遺言者の意思を実現すること』と示され、今回の法改正ではこの考えを条文中に盛り込んだものとなります。
2項
2019年の法改正により新しく追加された条文です。
この条文は、遺贈するものを指定した「特定遺贈」について遺言書に記載されている場合に適用され、その遺贈の実行は遺言執行者のみが行うこととされています。
この条文も1項と同様、過去の裁判例を立法化したものです。
その裁判は「本来、Aさんに遺贈されるべきだった不動産を相続人が勝手に自分名義にしてしまった場合、遺贈を受けるはずだったAさんは誰に対してその名義を自分に変更する請求をすればよいのか?」というものです。
この裁判のなかで裁判所は『遺言執行者がいる場合はその請求は遺言執行者に対してのみ可能で、勝手に自分名義にした相続人に対しては請求できない』との判決を下しました。
この考えを反映させて追加されたのがこの条文ですが、実務上の考え方は法改正前からは変わりありません。
3項
遺言執行者の義務や責任について規定されています。
準用のもとになっている条文は「委任」について、その受任者が負う義務や責任が規定されていますが、このルールが遺言執行者に対しても適用されます。
下記「関連条文」のなかの『受任者』の部分を『遺言執行者』に置き換えて読んでみてください。
関連条文
民法第644条 受任者の注意義務
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
民法第645条 受任者による報告
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法第646条 受任者による受取物の引渡し等
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
第2項
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
民法第647条 受任者の金銭の消費についての責任
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法第650条 受任者による費用等の償還請求等
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
第2項
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
第3項
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。