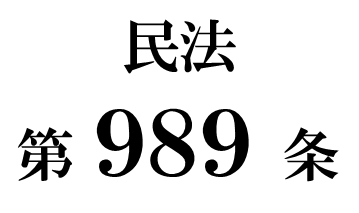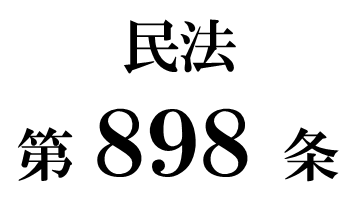民法第1022条 遺言の撤回
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
意訳
遺言を書いた人は、法律で定められた遺言の書き方の方式に従って、前に書いた遺言の全部または一部をいつでも撤回することができる。
条文解説
この条文は一度書いた遺言書を撤回する方法について書かれたルールです。
遺言書は書いた人が亡くなってはじめて効力をもつため、存命中はいつでも何度でも書き換えることができますし、破棄することもできます。
もし、一旦は遺言書を書いたものの、後になって気持ちや考えが変われば前に書いた遺言書を撤回することも可能です。
この条文では、前に書いた遺言書を撤回するためには、法律で定められた遺言の方式に従ってこれを行うことができると定められています。つまり「遺言の撤回は遺言で」行うことができるということです。
ただし、条文には「遺言の方式に従って」としか書かれておらず、遺言の方式までは指定されていませんので、たとえば自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも可能ですし、その逆も可能です。
なお、2020年からスタートした法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用されている場合に、保管中の遺言書を撤回するためには、法務局に対して撤回の請求を行わなければなりません。
ただし、法務局に対して行う手続きはあくまでも“保管の撤回”であって、遺言の撤回とは異なります。
遺言自体を撤回するためには法務局から返却された遺言書を破棄したり、先述のように遺言による撤回を行わなければなりません。
いずれの場合においても、もし遺言を書いた後に気持ちや考えが変わったにもかかわらず、前の遺言の撤回や書き換えをせずに放置しておくと、その遺言が効力をもってしまい、遺言者の遺志と異なる遺産分割が行われる可能性がありますので注意が必要です。